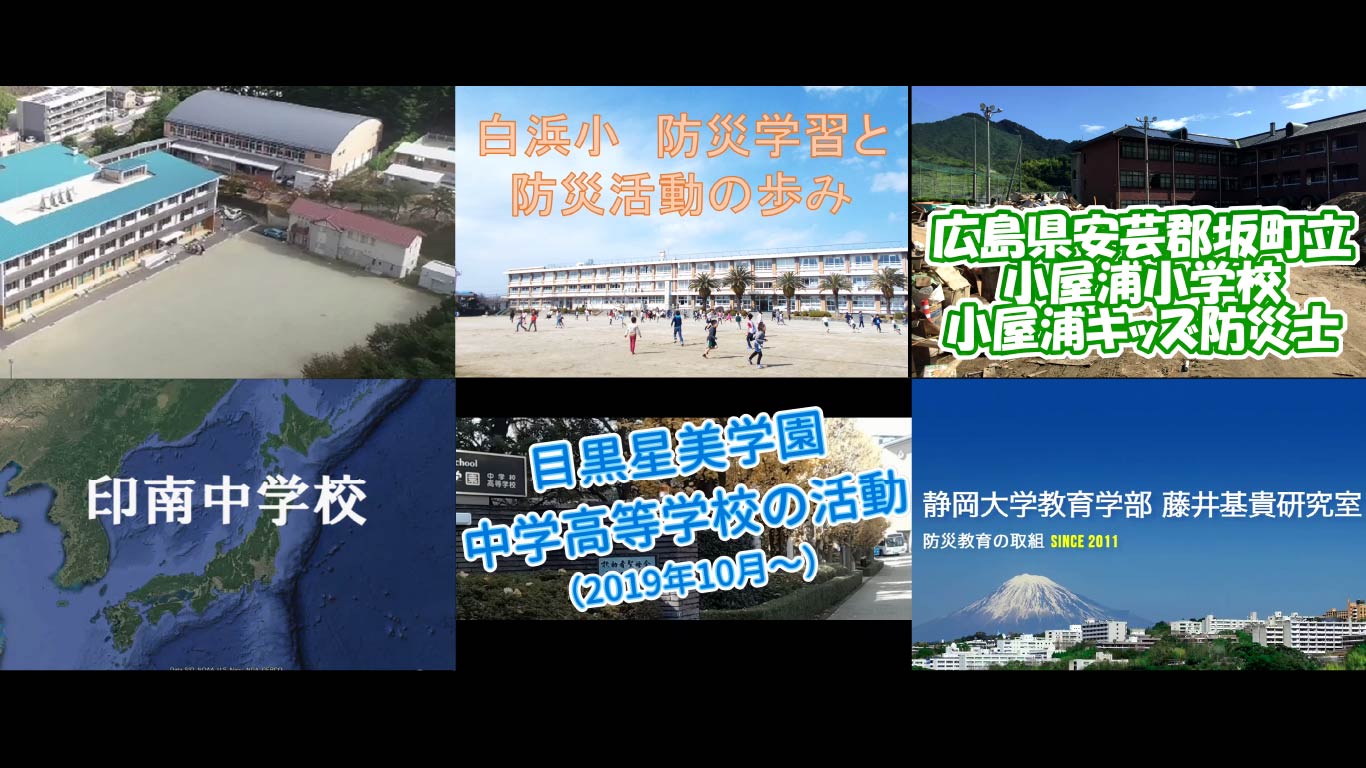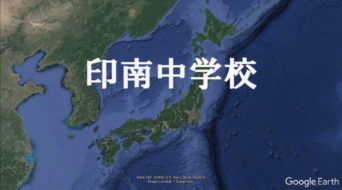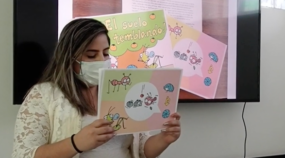年度別報告
グランプリ
ぼうさい大賞
-
 2023.02.14
2023.02.14仙台市立七郷小学校
- 令和4年度
- ぼうさい大賞
-
 2023.02.14
2023.02.14むかわ町立鵡川中学校
- 令和4年度
- ぼうさい大賞
-
 2023.02.14
2023.02.14龍谷大学政策学部 石原凌河研究室
- 令和4年度
- ぼうさい大賞
-
 2023.02.14
2023.02.14兵庫県立和田山特別支援学校
- 令和4年度
- ぼうさい大賞
-
 2022.01.13
2022.01.13和歌山県立和歌山商業高等学校
- 令和3年度
- グランプリ
- ぼうさい大賞
-
 2022.01.13
2022.01.13阿南市立津乃峰小学校
- 令和3年度
- ぼうさい大賞
-
 2022.01.13
2022.01.13気仙沼市立鹿折中学校
- 令和3年度
- ぼうさい大賞
-
 2022.01.13
2022.01.13愛媛大学 防災リーダークラブ
- 令和3年度
- ぼうさい大賞
-
 2022.01.13
2022.01.13埼玉県立日高特別支援学校
- 令和3年度
- ぼうさい大賞
-
 2021.01.15
2021.01.15宮城県立支援学校女川高等学園
- 令和2年度
- グランプリ
- ぼうさい大賞
-
 2021.01.15
2021.01.15坂町立小屋浦小学校 4年生
- 令和2年度
- ぼうさい大賞
-
 2021.01.15
2021.01.15印南町立印南中学校
- 令和2年度
- ぼうさい大賞

優秀賞
-
 2023.02.14
2023.02.14阿南市立橘小学校
- 令和4年度
- 優秀賞
-
 2023.02.14
2023.02.14ジュニア防災リーダークラブ(中学生)
- 令和4年度
- 優秀賞
-
 2023.02.14
2023.02.14愛媛県立松山工業高等学校
- 令和4年度
- 優秀賞
-
 2023.02.14
2023.02.14静岡大学教育学部 藤井基貴研究室
- 令和4年度
- 優秀賞
-
 2023.02.14
2023.02.14埼玉県立日高特別支援学校
- 令和4年度
- 優秀賞
-
 2022.01.13
2022.01.13阿南市立橘小学校
- 令和3年度
- 優秀賞
-
 2022.01.13
2022.01.13陸前高田市立高田第一中学校
- 令和3年度
- 優秀賞
-
 2022.01.13
2022.01.13目黒星美学園中学高等学校
- 令和3年度
- 優秀賞
-
 2022.01.13
2022.01.13静岡大学 教育学部 藤井基貴研究室
- 令和3年度
- 優秀賞
-
 2022.01.13
2022.01.13千葉県立東金特別支援学校
- 令和3年度
- 優秀賞
-
 2021.01.15
2021.01.15西尾市立白浜小学校
- 令和2年度
- 優秀賞
-
 2021.01.15
2021.01.15徳島市津田中学校 防災学習倶楽部
- 令和2年度
- 優秀賞

お知らせ
-
2021.07.30
徳島県立阿南支援学校の実践報告をUPしました
-
2021.06.21
令和3年度1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」の応募受付開始しました
-
2021.06.10
高知県大方児童館の実践報告をUPしました
-
2021.06.04
阿南市立橘小学校の実践報告をUPしました
-
2021.05.31
令和2年度 ぼうさい甲子園式典掲示用展示物について